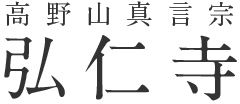淡彩日記

「烏枢沙摩明王の会(仮称)」を作りたいと思っています。
烏枢沙摩明王 の会(仮称)のごあいさつ
8月24日の烏枢沙摩明王お披露目法会に向けて現在準備を進めています。

合わせて、現代において、人と人のつながりが希薄になりがちな中、人々が本来持つ心の清々しさと安らぎを育めるよう、学びと助け合いの場として「烏枢沙摩明王の会(仮称)」の設立を目指し準備を進めています。会を作りたいと思った背景について、お話させてください。
古来より、人と人とが助け合うことは自然な営みでありました。厳しい自然の中で生き抜くには、互いに支え合うことが欠かせません。誰かを助けるために率先して動いてくれる人は尊敬され、互いに助け合う仲間の安全を祈り、敬意を払うことは、自らの身を守ることにもつながる大切な教えとして受け継がれてきました。
一方、現代は、情報技術が発達し、五感を楽しませるモノは次々と消費できる時代です。とはいえ、いざという時、人と人とで助け合うことでしか乗り越えられない局面が誰にでも訪れます。その時のために、個人の範囲を超えた「助け合いの共同体」と関わることが大切です。
そうした共同体と関わるのは、楽しいことばかりではないかもしれません。多くの人と向き合うことが面倒に感じられたり、時には苦しく思うこともあるでしょう。けれども、「助けてほしい」と声を上げなければ、周囲の人が助けたくても助けられないということもあります。心の中を素直に話せるつながりを育むことは、目先の楽しみだけでは得られない深い味わいのある営みです。
仏教では、「苦しみ」は必ずしも避けるしかないものではなく、むしろその只中にある時こそ、真に自己を支えている「苦の滅(くのめつ)」に気づく機会であると説かれます。真言宗で普段お唱えする理趣経(りしゅきょう)には「生きとし生けるものは本来、清々しい」と記されています。苦の滅に気づき、人生を心穏やかなものとできるよう、そうした心を育む場を整備する必要があります。
かつてお寺は、人と人とが共に生きていけるよう、寺子屋や地域の寄り合いの場として機能していました。そこでは、目先の楽しみにとらわれず、共に語らい、一緒にご飯を食べ、ご詠歌などの音楽を唱え、学びや冥想を通して日常的に深く内省し、一人ひとりのペースで時間をかけながら、心の中に自信や勇気を育み、五感を超えた深い安らぎと人生の妙味を味わっていました。
現代でも、そうした場はなくなってしまったわけではなく、探せば実際にありますし、深い安らぎと共に生きている方々はおられます。そこで、弘仁寺においても、あらゆる人に開かれた、現代と古き良き時代とが共存できる道場を設けることで、今を生きる人々の安らぎと深い楽しみを増すべく、尽力してまいりたいと存じます。
今回、心の浄化において最も霊験あらたかである仏さま、烏枢沙摩明王さまをお迎えしましたのは、烏枢沙摩明王さまが、私達の苦しみを滅し尽くし、私達が穏やかに生きることを見守り、応援してくださる仏さまだからです。
人と人とで助け合うのが大事だとわかっていても、最初はなかなか勇気が出ません。人生経験の中で苦しみや悲しみを味わう中で、人のことを信じるのが難しくなることもあります。また、人からは愛されたいのにどうしても自分から人に愛情を向けるのが怖いこともあるでしょう。
私達が苦しみの只中にある時、過去の苦しみから抜け出せない時、未来の不安が消えない時、烏枢沙摩明王はそうした苦しみを滅して、私達が本来持つ心の清々しさに気づかせてくださいます。
こうしたことから、弘仁寺に昔ながらの人と人との信頼関係を醸成する共同体を再び作るのであれば、烏枢沙摩明王を拝することが現代の人にとって大きな助けになると信じ、お大師さまの四恩十善の教え(父母・国王・衆生・仏法僧の三宝の四つの恩を思い、十善戒を保つ教え)にかなうものと拝察します。
当会(仮称:烏枢沙摩明王の会)は、会に参加する人同士が互いに学びを深め、互いに助け合うことで、心を清々しくし、身心が健康で心穏やかに生きることを目的とします。対面での集まりだけでなくオンラインも活用できればと考えています。当会の理念にご賛同いただけます方、興味をもたれた方は、弘仁寺までご連絡ください。皆様と共に当会を盛り上げていけますよう力を尽くしてまいります。会の名称等、詳細は、8月24日のお披露目会にてお知らせいたしますので、当日どうぞお参りくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
令和7年7月吉日
弘仁寺 住職 森田眞源 拝
当日お越しの方へ、カレーのお接待を用意しますので、お問い合わせより、8月24日〇〇名参加とお知らせください。