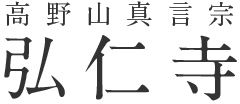淡彩日記

弘仁寺納骨堂「やすらぎ地蔵堂」新規申し込み受付中
多羅尊お迎え法会のご案内

この度、縁ありまして、多羅尊(別名:多羅観音菩薩)の絵像をお迎えすることになりました。多羅尊は、あらゆる仏様の中で最も慈悲深い仏様といわれています。多羅尊の慈悲で、心の中を浄化して頂きますようにお参りいたします。この日は、お釈迦様が悟りをひらかれた日でもあります。
どうぞ、お参りください。
(この日は平日ですので、お昼の部、夜の部の二回にわけて行います。)
日時令和7年12月8日
第一会、14時より 第二会、19時より
「烏枢沙摩明王の会(仮称)」を作りたいと思っています。
烏枢沙摩明王 の会(仮称)のごあいさつ
8月24日の烏枢沙摩明王お披露目法会に向けて現在準備を進めています。

合わせて、現代において、人と人のつながりが希薄になりがちな中、人々が本来持つ心の清々しさと安らぎを育めるよう、学びと助け合いの場として「烏枢沙摩明王の会(仮称)」の設立を目指し準備を進めています。会を作りたいと思った背景について、お話させてください。
古来より、人と人とが助け合うことは自然な営みでありました。厳しい自然の中で生き抜くには、互いに支え合うことが欠かせません。誰かを助けるために率先して動いてくれる人は尊敬され、互いに助け合う仲間の安全を祈り、敬意を払うことは、自らの身を守ることにもつながる大切な教えとして受け継がれてきました。
一方、現代は、情報技術が発達し、五感を楽しませるモノは次々と消費できる時代です。とはいえ、いざという時、人と人とで助け合うことでしか乗り越えられない局面が誰にでも訪れます。その時のために、個人の範囲を超えた「助け合いの共同体」と関わることが大切です。
そうした共同体と関わるのは、楽しいことばかりではないかもしれません。多くの人と向き合うことが面倒に感じられたり、時には苦しく思うこともあるでしょう。けれども、「助けてほしい」と声を上げなければ、周囲の人が助けたくても助けられないということもあります。心の中を素直に話せるつながりを育むことは、目先の楽しみだけでは得られない深い味わいのある営みです。
仏教では、「苦しみ」は必ずしも避けるしかないものではなく、むしろその只中にある時こそ、真に自己を支えている「苦の滅(くのめつ)」に気づく機会であると説かれます。真言宗で普段お唱えする理趣経(りしゅきょう)には「生きとし生けるものは本来、清々しい」と記されています。苦の滅に気づき、人生を心穏やかなものとできるよう、そうした心を育む場を整備する必要があります。
かつてお寺は、人と人とが共に生きていけるよう、寺子屋や地域の寄り合いの場として機能していました。そこでは、目先の楽しみにとらわれず、共に語らい、一緒にご飯を食べ、ご詠歌などの音楽を唱え、学びや冥想を通して日常的に深く内省し、一人ひとりのペースで時間をかけながら、心の中に自信や勇気を育み、五感を超えた深い安らぎと人生の妙味を味わっていました。
現代でも、そうした場はなくなってしまったわけではなく、探せば実際にありますし、深い安らぎと共に生きている方々はおられます。そこで、弘仁寺においても、あらゆる人に開かれた、現代と古き良き時代とが共存できる道場を設けることで、今を生きる人々の安らぎと深い楽しみを増すべく、尽力してまいりたいと存じます。
今回、心の浄化において最も霊験あらたかである仏さま、烏枢沙摩明王さまをお迎えしましたのは、烏枢沙摩明王さまが、私達の苦しみを滅し尽くし、私達が穏やかに生きることを見守り、応援してくださる仏さまだからです。
人と人とで助け合うのが大事だとわかっていても、最初はなかなか勇気が出ません。人生経験の中で苦しみや悲しみを味わう中で、人のことを信じるのが難しくなることもあります。また、人からは愛されたいのにどうしても自分から人に愛情を向けるのが怖いこともあるでしょう。
私達が苦しみの只中にある時、過去の苦しみから抜け出せない時、未来の不安が消えない時、烏枢沙摩明王はそうした苦しみを滅して、私達が本来持つ心の清々しさに気づかせてくださいます。
こうしたことから、弘仁寺に昔ながらの人と人との信頼関係を醸成する共同体を再び作るのであれば、烏枢沙摩明王を拝することが現代の人にとって大きな助けになると信じ、お大師さまの四恩十善の教え(父母・国王・衆生・仏法僧の三宝の四つの恩を思い、十善戒を保つ教え)にかなうものと拝察します。
当会(仮称:烏枢沙摩明王の会)は、会に参加する人同士が互いに学びを深め、互いに助け合うことで、心を清々しくし、身心が健康で心穏やかに生きることを目的とします。対面での集まりだけでなくオンラインも活用できればと考えています。当会の理念にご賛同いただけます方、興味をもたれた方は、弘仁寺までご連絡ください。皆様と共に当会を盛り上げていけますよう力を尽くしてまいります。会の名称等、詳細は、8月24日のお披露目会にてお知らせいたしますので、当日どうぞお参りくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
令和7年7月吉日
弘仁寺 住職 森田眞源 拝
当日お越しの方へ、カレーのお接待を用意しますので、お問い合わせより、8月24日〇〇名参加とお知らせください。
烏枢沙摩明王(うすさまみょうおう)お披露目法会のご案内

このたび、ご縁あって弘仁寺に烏枢沙摩明王(うすさまみょうおう)の尊像をお迎えし、百日間の開眼修法を厳修いたしました。
つきましては、「烏枢沙摩明王お披露目法会」を厳かに執り行います。
どうぞお参りくださいますようご案内申し上げます。
ーーーーーーーーーーー
8月24日(日)
11時より
弘仁寺 本堂にて
ーーーーーーーーーーー
当日は、お昼ごはんにスパイスカレーのお接待を用意します。
住職が1週間煮込んでつくるカレーを召し上がっていただきながら、穏やかなひと時が過ごせますことを祈念しております。
どなたでも参加いただけますので、ご参加いただける方は、お問い合わせより8月24日参加希望とメッセージをお願いします。
皆様のお越しを心よりお待ち申し上げています。
心を浄化する功徳あらたかな烏枢沙摩明王を、このたび弘仁寺にお迎えいたします。
弘法大師(お大師さま)は1200年前から、ずっと一つの普遍的なメッセージを伝え続けてこられました。それは、「一切衆生──全ての生きとし生けるものの心の本源には、仏さまと等しく、清々しく澄み切った、安らかで穏やかな心がある」ということです。

この仏心はどのような心かというと、人が幸せにしているのを自分のことのように喜べる心です。人が苦しみ、悲しんでいるのを自分のことのようにいたみ、その苦しみをとってやりたいと願う慈悲の心です。あらゆるこころのはたらきが実体のない空であると見抜く智慧の心です。
私たちはその仏心を携えて「オギャー!」と生まれてきます。ですが、言葉を覚え、社会で成長していくにつれて、他の人からイヤなことを言われることもあるでしょう。蔑(さげす)まれることもあるでしょう。いじめられることも仲間はずれにされることもあるかもしれません。
そうして生じるのが「自分を守ろうとする心」です。本来の仏心ではないこの心が、過ぎ去った出来事を思い出すたびに暴走し、これを仏教では「煩悩(ぼんのう)」と呼びます。
その中でも瞋(しん)という激しい怒りの煩悩は、自分と人を比較して、自分を蔑みはずかしめた相手を激しく憎む心です。煩悩が暴走すると、心の中は憎悪の炎の黒い煙によって暗く覆われ、戦場のように乱れ、尽きることのない苦しみにさいなまれます。自らを守ろうとして自らが傷つく、これが煩悩の恐ろしさといえます。
この煩悩の構造は、現代社会のあり方にも深く関わっています。現代社会において、たとえ今後ロボットやAIなどの技術がどれほど進化したとしても、人間の「煩悩の暴走」を制御することは難しいかもしれません。
といいますのも、科学技術の開発が推進されるかどうかは、常に「経済的価値が増すかどうか」という価値判断に基づいているからです。
しかし、その判断基準には「優劣の比較」が必ず含まれています。そして、この比較こそが、人の心から穏やかさを奪い、煩悩の暴走を生む原因なのです。
経済成長や科学技術の発展を追い求めるだけでは、自分を守ろうとするあまり、かえって自分を傷つけるという矛盾が繰り返されてしまいます。
さらに、ロボットやAI技術は、「自分と他人の優劣を比較する心」を助長し、技術が進めば進むほど、あらゆるものごとを比較によって捉えさせようと、人の心に働きかけているのです。
ですが実は、2500年前からこの「自分を守ろうとして自分を傷つける」という煩悩の問題に真正面から取り組んできたのが仏教徒でした。お釈迦さま、お大師様の願いは、人々を煩悩の苦しみから救うことに他なりません。
仏教の歴史は、煩悩の暴走に巻き込まれている心を解放する道のりとして始まりました。
ですが、自分を守ろうと暴走する煩悩を自力だけで制御するには、煩悩の主張に振り回されない大変な勇気と、煩悩のいう理屈を幻だと打ち砕く絶大な知性、そして煩悩のもつ本来けなげなはたらきへの限りない愛情を伴った慈悲心が必要です。
そこで頼りになるのが、「信じられる師(明師)」の存在です。
今の時代でも、煩悩とひたむきに対峙している人は確かに存在しています。そのひたむきな生き様を見つめるのです。煩悩に真正面から向き合い、煩悩の暴走に振り回されなくなった人を見つけられたなら、自分も同じようにしようと思えるようになります。
やはり、人は結果にこだわらず、ただひたむきに頑張っている人を見ると、自然と元気をもらうようです。このことに理屈はなく、なぜかは分かりませんが、ひたむきに頑張る人を、私たちはただ、見つめていたいのです。
さて、ここまで、煩悩の暴走を無くせば楽になるということがわかっても、信頼できる明師が最初は中々見つからないかもしれません。
こういうとき密教では、自力ではどうにもならないほど強力な煩悩の暴走をおさめるために、浄化に特化した仏様のお力にすがるのをおすすめいたします。
まずは、修行が成就するようにお大師様をお参りします。「同行二人(どうぎょうににん)」お大師様と二人連れの思いを心に刻みながら、繰り返し、南無大師遍照金剛とご宝号をお唱えします。煩悩の暴走という問題に対して、お大師様と共に歩むと思えば、日々の希望となるはずです。
さらに、大日如来が変身されたお姿の不動明王をお参りします。不動明王の智慧の剣と智慧の炎を持って「この嫌な記憶と煩悩との結びつきを切り払い、焼き尽くして下さい」と願い、のうまくさーまんだーばーざらだん せんだーまーかろしゃーだーそわたや うんたらたー かんまん!と不動明王の真言を繰り返しお唱えします。やがて煩悩と出来事の結びつきは切り離され、跡形もなく焼き尽くされていきます。そうして次第に静かな喜びにつつまれた穏やかな心になっていくでしょう。
このように、お大師様、お不動様を日頃からお参りしていても、どうしても制御しきれない煩悩があるかもしれません。そうした心の奥にある煩悩に対して、密教では特別な仏さまのお力をいただくという方法がございます。
その仏様は、私たちの心の奥底にある最も醜く感じられる部分、お大師様やお不動さまに見せることさえはばかられる恐れの感情、自分の性格の問題に対する苦しみ、人から蔑まれるようなコンプレックス、トラウマと感じていることなど、相談することが恥ずかくて出来そうにない深い悩みを清らかに浄化してくださいます。
その仏様こそ、火頭金剛(かずこんごう)、穢積金剛(えしゃくこんごう)とも称される烏枢沙摩明王(うすさまみょうおう)です。トイレの神さまとしても親しまれるこの仏さまは、不空成就如来(お釈迦さま)が慈悲の心で変身されたお姿といわれています。四つの手に剣と、紐と、宝の棒と、三叉のホコをお持ちです。
烏枢沙摩明王は、火光三昧(かこうざんまい)に入られて、超高温の熱線によって私たちの心の中に固く固着した暗い記憶を焼き尽くして下さいます。そうして、つらい感情を伴う記憶から、感情と記憶を切り分けます。
烏枢沙摩明王のご真言、
①おんしゅりまり ままりまり しゅしゅり そわか
②おんくろだのう うんじゃく そわか
を何度も唱えてお参りするうちに過去の出来事が「ただの出来事」となり、思い出しても煩悩が動かなくなれば、心は真に静まります。
浄化とは、嫌な出来事と思っていることは、実は実体のない空(くう)だと気づくことです。智慧によって苦しみを空(くう)じることです。それにより煩悩が暴走する対象が幻だと気づければ、煩悩に振り回されることはなくなります。
このような教えと修行の実践を背景に、弘仁寺では今後さらに清浄な心を育む道場となるべく努めてまいります。
さて、本年は弘仁寺開創して125年となります。境内に開創25年の記念碑が建っておりますのでそこから丁度100年となります。125年の節目に開創の由来に立ち返り、清浄な心を実感できる霊場となるべく、いくつかの事業を計画しております。
まず、この度、ご縁があり烏枢沙摩明王の身の丈二尺三寸五分(約70センチ)の絵像(掛け軸)を弘仁寺にお迎えいたします。お披露目は約一か月後の予定です。

さらに当山で既におまつりし、おかげをいただいております女尊で即身成仏されておられる仏さま、大変浄化の力の強い多羅尊(多羅観音、ターラー尊)の絵像(掛け軸)を秋から冬ごろにかけてお迎えする予定です。
弘仁寺が皆さまにとって清浄な心を実感できる霊場となるよう、開創の際の発起人の方々の願いを成就できますように、お大師様、お不動さま、烏枢沙摩明王、多羅尊におすがりしてお参りしてまいりますので、どうぞ皆さま方も、ご信心ご参拝くださりますよう御案内申し上げます。
弘仁寺は、開山の趣旨にのっとり、あらゆる人が平等に救われる霊場をめざします。皆さまのご支援ご協力を心よりお願い申し上げます。
11弦ギターと篠笛コンサートのお知らせ

4月16日19時より弘仁寺において辻幹雄さんとヨーコ・カンタルーナさんをお迎えして、弘仁寺 春の夜の音楽と法話会を開催します。
開場は18時30分より、当日チケット4000円となっております。
ご参加希望の方はお問合せください。
12月28日餅つき大会開催します!
本日12月28日昼11時から12時半まだ予定通り餅つき大会を開催します。どうぞお越しください。
鎮魂の音楽と法話のゆうべを開催します

11弦ギター奏者の辻幹雄さんをお迎えして、鎮魂の演奏と法話のゆうべを開きます。
お申込みの方はホームページのお問合せよりご連絡ください。
餅つき大会のおしらせ
弘仁寺での餅つき大会は今年で4回目になります。どなたでも飛び入り参加歓迎ですのでどうぞお越しください。もちは3回つきます。当日初めて来られる方も大歓迎です。
日時 2023年12月30日 11時より12時半まで
場所 弘仁寺 境内
参加費 無料です

仏教お話会「心の中に辞書がある!?」のご案内
令和5年7月16日(日)13時より弘仁寺で「仏教お話会」を開催しますのでご案内します。
心は言葉でできています。私たちの心の中には、真っ白なノートがあって、そこに誰かから聞いた言葉とその意味をどんどん書き留めているのです。赤ん坊の頃から、私たちは言葉の見た目(視覚)、音のトーン(聴覚)、匂い(嗅覚)、味(味覚)、肌触り(触覚)など、五感で言葉とその意味を感じ取り、メモを取り続けてきました。
大人になると語彙が増え、心の中には個々に異なるオリジナルな辞書ができます。ある人の辞書には五感を刺激するメモやイラストがたくさん書かれており、まるでカラフルでワクワクする百科事典のようです。また、別の人の辞書は、言葉とその意味が一つだけ書かれた英単語帳のような形をしているかもしれません。
そして、この辞書こそが、心に楽しみや苦しみを感じさせるのです。私たちの幸せや不幸の感覚は、この辞書の中身がどうなっているかによって大きく変わります。いうならば心の中の辞書こそが心の本体ということもできます。ですので、今回のお話会では、心の中の辞書に焦点を当て、注目していきます。
心の中の辞書は本来、常に改訂できるノートの集まりです。しかし、分厚い本や辞書、学校、親や友達、テレビ、映画、小説、論文、マンガ、アニメでおぼえた言葉の意味は、最初から固定されているように感じられるかもしれません。言葉の意味が心の中で変えていけるなんて、最初はなかなか信じられないでしょう。
他人から「正しい」と教えられた言葉の意味を心の中で変えていくのは、初めはためらわれるかもしれません。誰かから「この言葉は書き換えてはいけない」と言われたと感じる人は、心の中のノートに書いた言葉を修正するのに勇気が必要になるでしょう。
しかし、自分の心の中の辞書を書き換えること(改訂すること)は自分にしかできません。五感を使って再び体験し、心の中のノートを書き換え、心の中の辞書を改訂する勇気を持ちましょう。そうしたら、「ある言葉を聞いたら急に怒りが爆発する」といったことが無くなるはずです。
子供の頃から五感を通じて言葉を学ぶと、心の中の辞書が個々に異なるものだと信じられるようになります。その結果、相手の言っていることの意味が分からないときには、相手の心の中の辞書を読み解こうと思えるようになるでしょう。人を思いやるというのは、人の心の中の辞書を読むことなのかもしれません。そうなりますと、最初は意見が合わなくても、即座に相手が悪い人だと決めつけなくなるでしょう。相手の心の中の辞書を研究し、読み解いているうちに、相手と分かり合えるようになる可能性は残されています。
仏教では心の中のノートにどのように言葉をメモするか、そして出来上がった辞書をどう書き換えていくのかについて、何千年もの間、観察し、研究してきました。心の中の辞書の書き換え方を学ぶことは、心の中を明るく豊かにしていくためにとても良い学びとなるはずです。
ご興味のある方は、どうぞお気軽にお越し下さい。
「仏教お話会」
日時 7月16日(日)13時から16時
場所 弘仁寺 長崎市出雲1丁目17-23
参加費 3000円
嫉妬と随喜(ずいき)その1
私たちはやっぱり、自分が可愛いものです。誰にでも大なり小なりそういうところがあります。そして、そのこと自体が絶対にいけないというわけではありません。嫉妬自体は、心の自然な働きの一つだからです。
人間ですから、人生のある時期、自分のことにしか興味がもてず「人が善いことをするのを喜べなかったり、人の幸せを喜べない気持ち」つまり「嫉妬」の気持ちに振り回されてどうしようもなく、そんな自分が嫌になることがあるかもしれません。
ですが、私たちは、嫉妬心が自然にあると同時に「人の善い行いを喜ぶ気持ち、幸せを喜ぶ気持ち」を育てることができます。江戸時代まではそれを「随喜(ずいき)」の気持ちと呼んで大切にしていました。弘法大師は『十住心論』巻第九にて、「喜とは随喜(他者の善行を喜ぶこと)です。他者の善をみて自分のことのように喜ぶことをいいます。あらゆる人を平等に見て、嫉妬の心を離れるからです」とおっしゃっています。
善行とは、苦しみを減らしていく行いです。苦しみが少なくなり気にならなくなった状態を楽といいます。
あなたがもし、どうしようもないほど嫉妬に振り回されていると感じるとしたら、それは心の全体像を学ぶ時期がきているのかもしれません。倶舎論という仏教の基礎学では心の中に20種類以上の苦しみを増やす心(煩悩)があると説きます。それは誰にでも自然にあるのです。最初から煩悩が全然無い人はいないのです。そして20数種の煩悩の一つでも対処されないまま放置されていると、苦しみが減らずに心の中がいつもどんよりと濁ったようになり、いつまでも清々しくなりません。本来、仏教の教えは、そうした心の苦しみ(にごり)を減らし、心を清々しく明るくするために説かれています。
そのゴール地点が般若心経の教え、般若波羅蜜多です。ですが、いきなりゴールに行くのは大変ですよね。究極的には一切がみな空(くう)だとしても、いきなり空を体得するのは簡単ではありません。「嫉妬がやめられない」等、今の悩みに切実さと実体感がある間は、それを軽くする教えを学ぶところから始めてみましょう。弘仁寺での勉強会では、心を軽くする仏教の教えを初歩的なところから一つ一つ学んでいきます。
少しずつ心のねじ曲がりを正直に(まっすぐに)していき、心の中に隠していた思いを打ち開けていくにつれて、だんだんと人の善行を喜べない気持ちは治まり、人の善行を喜べるようになっていきます。
正直なところを打ち開ければ、私たちはみんな自分勝手な生き物なのかもしれません。人生を振り返ると、苦の減らし方なんて誰も教えてくれなかったような気がしてきますし、自然と苦を育てることばかりしていたような気がします。ですが、嫉妬するのにも、いつかは疲れますし、人の幸せを喜ばないのにもエネルギーがいるので、だんだん嫉妬するのにも飽きる日が来るでしょう。そうしているうちに、(人の幸せを喜ぶ)随喜の気持ちを育ててみようか、という気分になるかもしれません。随喜の種は私たちの心の中に確かにあります。随喜の種から芽が出て茎が伸び、いつか花を咲かせ、実をつける時がくるのを楽しみに待っています。今日もお読みいただきありがとうございました。
如意宝珠に願うもの
想像してみてください。この世のどこかに確かにある、あらゆる願いを叶える大きな大きな如意宝珠に私たちは何を願うのかを。自分の幸せ?それとも、家族の幸せ?はたまた、愛する人の幸せでしょうか?
この世に確かに実在する、如意宝珠よ、宝の珠よ。願わくは、過去、現在、未来、あらゆる場所のあらゆる時間に生きる、生きとし生けるもの全てに行き渡る功徳を雨のように平等に降らせてください。そしてその功徳によって生きとし生けるもの全てが、その在り方にあった智慧(変化を受け入れる穏やかさ)と慈悲(相手の苦しみを取って楽を与えたいという慈愛の思い)を得られますように。生きとし生けるものが皆、そして、あらゆる存在が皆、今日一日、誰からも声をかけられずとも、今日一日、誰からも褒められなくとも、今日一日、ただそこにいれたことは、それは幸せだと、感じられますように。 明日もまた、いろいろあっても幸せな一日になると信じて、穏やかなひと時をすごせますように。 今日もありがとうございました。