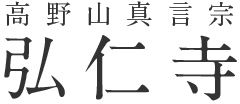淡彩日記

納骨堂のご案内


弘仁寺納骨堂「やすらぎ地蔵堂」新規加入者を先着で受付しております。
令和2年12月18日現在、A特大型、B大型の受付は終了しています。
C大型と、D中型、E個人壇の受付は引き続き行っております。
納骨堂の見学をご希望の方はお電話、又はお問い合わせフォームよりご予約下さい。お申込みをご希望の方も同様にお問い合わせ下さい。
<よくあるご質問>
Q:納骨壇には何人分のお骨が入りますか
A:一般的な7寸(直径約21センチ)のお骨壷の場合、C大型の納骨壇で6名様、D中型は3名様、個人壇は1名様のお骨壷を収めることが出来ます。又、お骨壷を小さいものに取り替えることによって、同じ納骨スペースにより多くの方を納骨することが出来ます。お骨壷を小さいものに取り替えることを検討される場合はご相談下さい。
Q:永代供養をお願いしたいのですが
A:弘仁寺では管理料として毎月1000円(年12000円)お預かりしています。永代供養をお考えの方には33年分の管理料として39万6000円お預かりしています。その後、合祀することになります。
Q:宗派は大丈夫でしょうか
A:弘仁寺は高野山真言宗のお寺ですので、各納骨壇には「南無大師遍照金剛」という御宝号が掲げられております。御宝号は現状から変更できませんので、現状でご納得いただけます方は、大丈夫です。

弘仁寺通信12号を作りました。

年末年始の行事案内です。
12月21日 お磨き会
12月30日 もちつき
12月31日 年越し護摩
1月3日 初護摩
2月2、7日 節分星まつり、豆まき
心を整えて、気持ちが自然と穏やかになりますように。
人と人の繋がりを信じられますように。
前に進めますように。
そんな願いを込めて。
何をどうしたら良いか、中々結論が出せないこんな時こそ、伝統的な行事を見直す時期なのかもしれません。
こうした行事の中には、幾多の困難を乗り越えて、私たちに命のバトンを繋いでくれた先人の智慧が凝縮されています。
お祭りを通して、ご自身の未来を発見してみませんか?
餅つき大会のお知らせ(令和2年分は終了)
12月30日11時より弘仁寺境内にて、ちんどん、祝い餅つきのかわち家さんと一緒に餅つき大会を開催します。
11時より第1回 100食
11時30分より 第2回 100食
12時より第3回 100食を予定しています。
つきあがり次第つきたてのおもちを無料でお配りします(無くなり次第終了)
ぜひ一緒におもちをつきましょう!当日飛び入り大歓迎です
沢山のお米が一つになって餅になるということから、餅つきには一致団結という意味があるそうです。
今年一年を振り返ったときに、人生観が変わるような経験をした方が多かったように思います。今までのような「今さえよければ、自分さえよければ」という考えではなく、世界中が心を合わせていくことが大切に感じられる年になりました。
我慢をすることが多くなる中、未来を担う子どもたちに思い出を作ってあげる機会が減る大変な一年でしたが、来年に向けて子どもたちの心がもっともっと明るくなるよう、子どもたちが将来に希望を感じてもらえるように、実行委員一同で準備をがんばります。大人も子どもも心をひとつに来年に向けてがんばりましょう。
(新型コロナ対策として、手指消毒、手袋、マスクの着用を行います)

12月8日に成道会(じょうどうえ)を開催します
お釈迦様がご自身の心を観察して悟りを開かれた日。自分の一年の心の動きを観察し、振り返る日です。2500年続いた仏様の教えが今年も一年続いたことをお祝いしましょう。朝10時から夕方4時の間で、来れる時間にお寺におこし下さい。お参り、冥想、おかゆのお接待をいたします。それぞれが少し立ち止まって、自分の心を見つめる時間を持ち、お釈迦様とのつながりを感じましょう。
来年をより良い一年にするために、自分の心を観察し、整える時間を過ごしてみませんか?

精霊船を作っています。



15日まで、残り少しですので、準備をがんばります!
弘仁寺納骨堂「やすらぎ地蔵堂」新規申し込み受付中
手作りの冊子(ZINE)を作って7月20日から8月18日までココウォークの本屋さんで販売することになりました。

ZINE(ジン)というのは個人やグループで作る少部数印刷の冊子のことです。内容もページもサイズも全て自由、作り手の好きに作られるからとても個性的です。住職も平成30年にできたチョージンという長崎のZINEグループに入れてもらって、去年からZINEを作っています。
今年は7月20日から8月18日までココウォーク5階TSUTAYA BOOKSTOREで「チョージン2019」というグループの作品展に参加します。
今年の3月から7月にかけて空いた時間にコツコツと書いていた原稿がまとまって、一冊の小さな手作りの冊子になりました。
タイトルは「ことばのひみつ ひみつのことば 2」です。
36ページの読みものです。
文は住職が書いて、題字と絵は坊守さんの作品です。
なんでZINEを書いたかと言うと……
「悟りを開く」とか「煩悩をなくす」と聞くと何だかとても難しい話に思われがちな仏教なんですが、お経を細かく読んでいると、生きている私たちの心が元気になるために、仏教はあるんだなぁと分かってきました。
そうして分かったことを、法話会で1時間話しただけではなかなか聞いている人に納得していただくのが難しいので、できるだけ分かりやすく順番に書こうと思って今回のZINEをつくりました。
仏教の空(くう)の教えは、元々はこころの奥底にある「恥ずかしさから、身動き取れなくなった自分」を立ち直らせるためにあるみたいなんですね。たくさんあるお経の中から、励ましになりそうなことばが書いてあるお経を紹介しながら、自分の言葉で柔らかく伝えられたらなぁと思って作りました。
作っている時のエピソードとしては……
まず、締め切りに間に合うのか?が一番心配なところでした。材料自体はコツコツと書き溜めているのですが、ただ書き溜めるだけでは、いつまでも中身に納得出来ません。
なので、締め切り間近、「今日必ず終わらせる。今日で書き上げる!」という気持ちになるのが大変でした。
今回、頑張るきっかけとなった出来事があとがきに書いてあります。ギリギリまで結論が決まりませんでしたが、その出来事があってジンの結論がでました。そこから一気に書き上げました。一番集中していたのは子供が寝た後の夜10時から朝4時くらいまでで、時間の経つをのを忘れるほど充実感がありました。それに、今回トークイベントにでないといけないというプレッシャーも書くための助けになりました。締め切りがあると頑張れますよね。
読んでもらいたいポイントとしては……
去年作らせてもらった「ことばのひみつひみつのことば1」では、「こころの中にある何かに気づく」がテーマでした。
今回の2では、こころの中の探求をさらに深めて、「こころの奥底に隠れている恥ずかしさと向き合う」がテーマです。
どこから読んでもらっても大丈夫ですが、それぞれのパートがお互いに補完しあってます。

今回、原稿の一部(6ページ分)公開します。
生きる中で悲しみと痛みを感じていらっしゃる皆さまへ、少しでもお役に立てましたら、幸いです。
ご入用の方はお問い合わせ下さい。(500円です。)
上の画像を押すとページが選択できます。拡大縮小もできます。
計画開始から、僅か2ヶ月で、納骨壇が無事納まりました。
令和元年6月24日、涼やかな風が吹く長崎の丘の上で、納骨堂への搬入がありました。令和元年5月1日の計画スタートから2ヶ月…ついに、この日がやってきたのです。当初は9月ごろの完成と思われていましたが、関係する皆さまのご尽力により、予想を遥かに上回る早さに驚かされます。ありがたいことです。
今回、新規設置される仏壇型納骨壇は36基です。
高野山奥の院にかかる、御廟の橋板が36枚で、全体を1枚と数えて金剛界曼荼羅37尊を表すことから、36は高野山では特別な数字です。




平和を祈る長崎の丘の上に、曼荼羅の仏さまに見守られながら、とこしえに安らう場所が出来ました。後は、外壁、屋根瓦の塗装、漆喰の塗り直しなどを経ていよいよ完成となります。令和元年の5月1日から始まったこの計画は、わずか2ヶ月で一つの形となりました。個人の力を越えた、不思議なはたらきに助けられているようです。関係する皆さまのご尽力のおかげです。ありがとうございます。
現在弘仁寺納骨堂「やすらぎ地蔵堂」では新規加入者の申込み受付中です。既に申込みが始まっておりますので、納骨壇をお考えの方は、どうぞお問い合わせ下さい。

供養はおいしい。
ご飯や果物、花といったお供えものと、お水をよき場所にお供えして、ローソクとお香を焚いて、座について、般若心経をあげます。
心の中では、空の世界に仮に結ばれた縁の儚さを懐かしみ、亡き人と私との来し方と行く末を幻のように感じつつ、それでも、今目の前にある愛おしい縁の和合を心ゆくまで味わう。
それが供養の醍醐味です。知恵と慈悲の出会いと別れ、離れていても想い合う時間……
供養は、心のごちそうなのかもしれません。
供養の味わいの豊穣さ、奥深さを一度味わうと、なぜ人類が手を合わせてきたのか分かります。まだ供養がよく分からないという方は、人任せにせず、自分で供養の醍醐味、味わってみてくださいね。
弘仁寺webページの目次
弘仁寺へのお問い合わせは、電話095-823-7759または、お問い合わせからメッセージを送ってください。
トップページ…トップページ中程に開催予定の行事案内が掲載されます。
弘仁寺について…住職紹介、弘仁寺の歴史
淡彩日記…ブログ(納骨堂案内や、行事詳細案内はこちら)
弔う…葬儀受付、法事受付、水子供養、お参りの作法について、お布施について
てら活…護摩、瞑想、写経、法話の案内
寺子屋「象浄会」…宗派を問わず誰もが参加できる寺子屋の案内。象さんのマークについて。
アクセス…写真がついていて分かりやすい。駐車場案内。
お問い合わせ…ここからメッセージを書いて送信いただければ、住職へメールが届きます。住職が読んで3日以内にお返事をします。お急ぎの際はお電話を。
いっちゃんの番組で弘仁寺を紹介してもらいました。
「いっちゃんのお寺でじぃーん」http://otera-de.com/という番組で、市原 隆靖さんとお話をさせてもらいました。
番組では、弘仁寺の様子を動画で撮ってもらっています。
まだ弘仁寺に行ったことがないという人には、動画でお寺の内部の様子がよく分かります。
話していて、思いました。
市原さん、素敵です。かっこいいです。
そして、うちのご信者さんには紳士です。
なにより仏教に対して真摯です。
素晴らしい機会をいただきました。
市原さんの今後のますますのご活躍と、無事「いっちゃんのお寺でじぃーん」108回達成を祈念しております。
機会がありましたら、また出たいです。ありがとうございました。